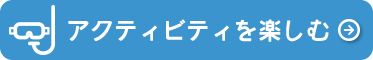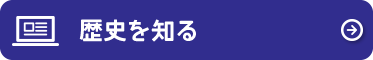歴史を知る
歴史を知る

1422年頃の那覇港の絵図(沖縄県立博物館所蔵)(無断転載禁止)

今から約500年前、沖縄本島では南山、中山、北山の三山を統一した尚巴志が、中国との交易船の出発地点として開いたのが那覇港の始まりといわれています。
その後、琉球王国の表玄関として中国や東南アジア、朝鮮、日本との貿易を行う東アジアの一大貿易港となりました。
初期には、中国の王朝に馬や硫黄(火薬の原料)などを贈答品として輸出し、絹織物や陶器、鉄器を輸入していました。琉球はこの貿易で中国から様々な文化的影響を受けました。今でも沖縄の風習や文化にその影響を垣間見ることが出来ます。その後、中国を始め朝鮮半島や東南アジアの国々と日本を結ぶ貿易の中間地点として、様々な国の品物や人、文化が集まる国際都市として賑わい、那覇港は、アジアを結ぶ海の交差点として、その影響は多大なものでした。
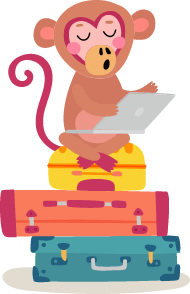
琉球王国6代目の王である尚泰久王が建立した「万国津梁之鐘」には、「琉球国は南海の勝地にして三韓(朝鮮)の秀をあつめ、大明(中国)をもって輔車となし、日域(日本)をもって唇歯となす。舟楫をもって万国の津粱となし、異産至宝は十方刹に充満す」とあり、琉球が中国、朝鮮、日本と進貢し、 シャム、マラッカ、スマトラ、ジャワなど東南アジアと広く貿易を行ったことで、豊かであったことを記しています。
1853年5月26日、ペリー提督が日本開国の目的で琉球に立ち寄りました。那覇港から上陸したペリー艦隊の一行は6月6日、首里城を訪問。その後、那覇港を拠点として、小笠原諸島、浦賀、函館などを訪問し、琉米和親条約や神奈川条約を結びました。
この黒船来航が江戸時代の終わりをつげる、明治維新へとつながっていきました。
1879年(明治12年)の琉球処分から数年の後、沖縄にも蒸気船が行き交い、1884年(明治17年)には、鹿児島と大阪とを結ぶ定期航路が開設、明治40年代には那覇港の本格的な整備が始まりました。1,200トン級の(約70m)の船を4隻同時に横付けできる桟橋や航路(幅72m、最大水深6.6m)が整備され、大正時代には145mの岸壁が完成し、3,000トン級の船も横付けできるようになりました。

太平洋戦争で壊滅的な打撃をうけた那覇港は、港内に沈没船があり、航路も浅く物資輸送が困難となっていました。戦後まもなく、米軍は重要な施設である港の復興に力を注ぎ大幅な改修工事を行いました。これにより、那覇港は20,000トン級、泊港は3,000トン級の船舶が係留可能となりました。
1954年(昭和29年)に那覇港が当時の琉球政府に、泊港が那覇市にそれぞれ返還されました。その後、安謝に新港の開発が進められ、1972年(昭和47年)には那覇港北岸、泊港、新港を那覇市が管理し、3港を一元化し、那覇港は重要港湾の指定を受けました。
2002年(平成14年)には那覇港管理組合が設立され、港湾管理者が従来の那覇市から沖縄県、那覇市、浦添市が出資する組合に移管されました。
Copyright(c) Naha Port Authority All rights reserved.